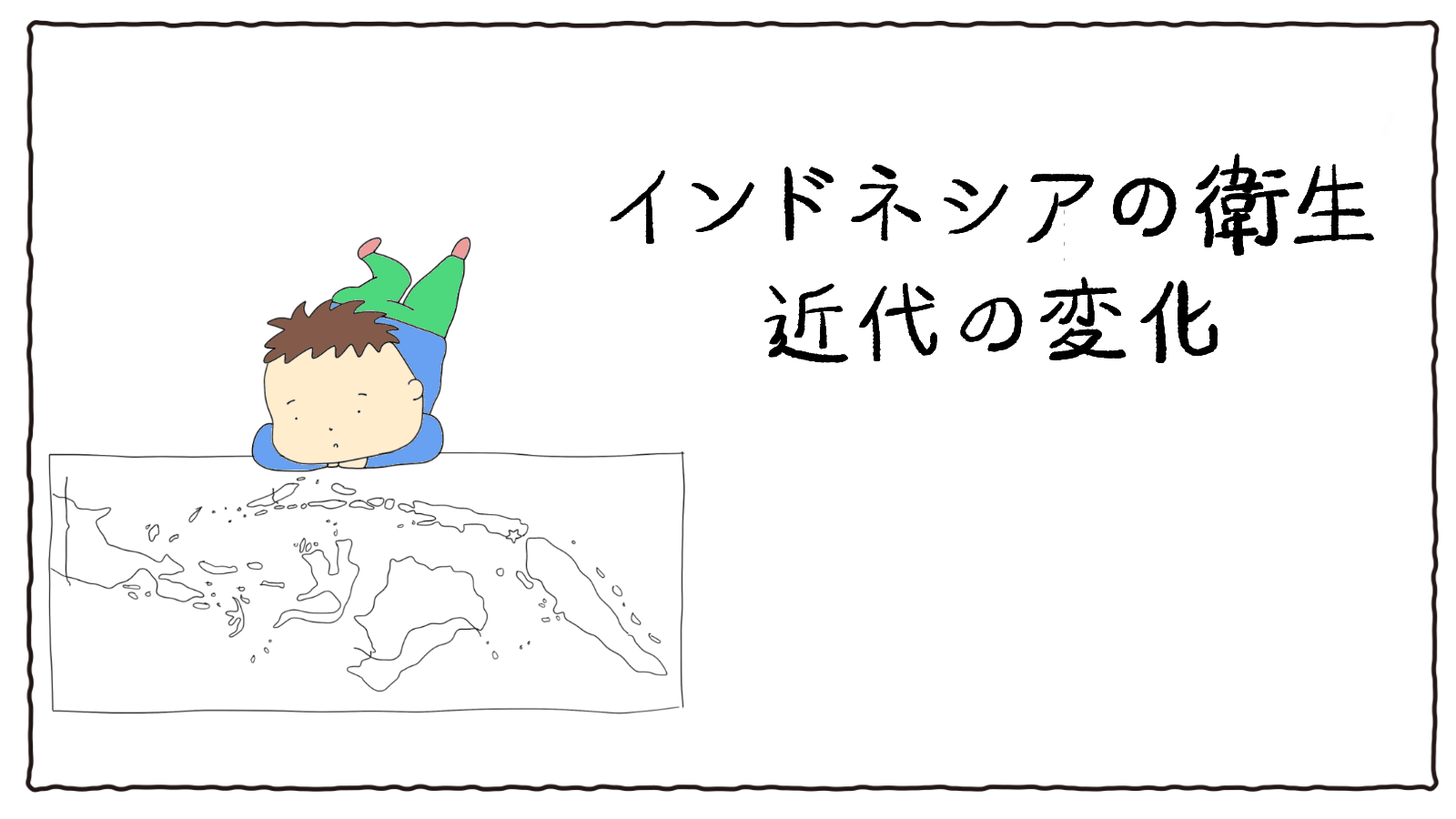水道の導入が続くインドネシア
豊かな水資源に恵まれたインドネシア人は、もともと、日に数度の水浴習慣を持ち清潔な伝統文化を築いていました。そこに、19世紀以降オランダを宗主国とする植民地化の流れで、西洋的な衛生概念が導入されていったわけです。
もちろん、《感染症の減少》や《効果的な応急手当ての普及》などで生活の質が向上した部分は大きいと思いますが、こうした他地域からの衛生文化の導入についてどこまでを歓迎するべきなのか、それぞれの人が意識を向けるべきではないかとも考えます。
水道の導入について
インドネシア人はもともと水浴習慣を持ち、河川水や湧水を活用して清潔な文化を築いていましたが、19世紀からは植民者であるオランダ人のために水道設備が導入されていきます。
ただ、1万6千の島々からなる島嶼国であるインドネシアでは水道設備の導入がスムーズに進まず、現在に至っても、上水道ですら限られた都市域への設置にとどまり、下水道はもっと限られた導入となっているとのこと。
しかも、国内移民が集中した首都ジャカルタ(人口密度は東京23区と同程度)では上水設備の保守管理が追いつかず、漏水や汚水混入の問題が深刻となっているようです。
もともとは自然な水で生活していたインドネシア人
日に数度の水浴習慣を持っていたインドネシア人は、水浴・洗濯・排泄などに河川水・湧水・雨水を活用してきました。そのため、衛生状況は地域の水資源の質に左右されていたようです。
河川水・湧水・雨水の活用は、現代日本で生活している私たちの感覚では、総じて不衛生なようにも感じられますが、代々共生してきた地域環境の自然な水は生きていく上で非常に相性が良かったとも考えられるのではないでしょうか。
その1つの例として、インドネシアと東アフリカの変更で働く学者のジータ・カスターラ氏は、西洋文化とほとんど接点のない、自然な水を活用し石鹸を使わない集団に対して「激しい労働をした後でも全く匂わない」ことに気付いたと発言しています。
悪臭の原因は皮膚にいる常在菌のアンバランスが招くという側面もあるため、皮膚にいる常在菌においては、自然な水が人々の体にいい働きをしていたとも考えられます。
軍とヨーロッパ人社会のために始まった水道設備
19世紀初頭から20世紀初頭にかけては、植民者であるオランダ人のために水道設備をはじめとする医療・衛生環境が導入されたようです。
代々その地で生活してきている原住民にとっては害のない自然な水も、外部からやってきたオランダ人にとっては安全ではなかったのでしょう。オランダ人にとっての衛生の維持のため、都市における近代的な水道設備の利用が進められました。
まずは首都であるジャカルタ(当時はバタビア市)から整備が進みます。
いきなり上水道施設から着手されたわけではなく、最初は自噴井を用いた給水設備、そこから上水道施設への転換、といくつかの段階を経て導入されたようです。
原住民にはなかなか受け入れられなかった水道設備
植民者であるオランダ人のために導入された水道設備ですが、原住民医師の養成の教育基盤整備などを背景に、原住民へも対象は広がったそうです。
しかし、手間がかかり出費もかさむ給水設備を、原住民はすぐには受け入れられなかったとのこと。
従来通り、河川などの自然な水を活用していたようで、当時、蘭領東インドの人口の7%だったヨーロッパ人が、ジャカルタ(当時はバタビア市)の給水量の78%に当たる水道水を利用していたといわれています。
こうした違いは格差を生むことにもつながり、当時、オランダ人は、自然な水を活用するインドネシア人の行為を後進性の特徴と捉えたとのこと。人種分類に加えて、衛生的か汚れているかというイデオロギー的な分類も生み出されることになりました。
課題の残るインドネシアでの水道設備導入
インドネシアの水道設備導入には現在も続く課題があり、上水道はまだまだ全国の都市域に限られた地域に設置されているにとどまり、下水道に至ってはジャカルタを含む12都市に限られている状況のようです。
※参考:2020年の統計で人口密度を見ると、インドネシア全体では141人/㎢でも、最も人口密度が低い北カリマンタン州では9人/㎢、人口密度が最も高い首都ジャカルタでは1万5907人/㎢にもなりこれは東京23区と同程度です
インドネシアは1万6千以上の島々からなる島嶼国であることもハードルとなり、上下水道の開発が進んできていないようです。
優先的に開発が進められたジャカルタでも、植民地期の上水道網を使い続けながら浄水設備を追加するという供給量の増やし方で現在に至っているとのこと。しかも、下水道は上水道網以上に整備が進んでいない状況です。
そうした状況のため、国内で最も進んだ上水道網を持つジャカルタですら、上水道の保守管理が追いつかず漏水や汚水混入の問題が深刻だといわれています。
参考:「“Yuk, Cuci Tangan Pakai Sabun!(さあ、石鹸で手を洗おう!)”―インドネシアにおける清潔さをめぐる社会文化変容についての一考察―」金子正徳、「<洗う>文化史」国立歴史民俗博物館・花王株式会社(編)p100-120「インドネシアにおいて「洗う」ということ 」金子正徳